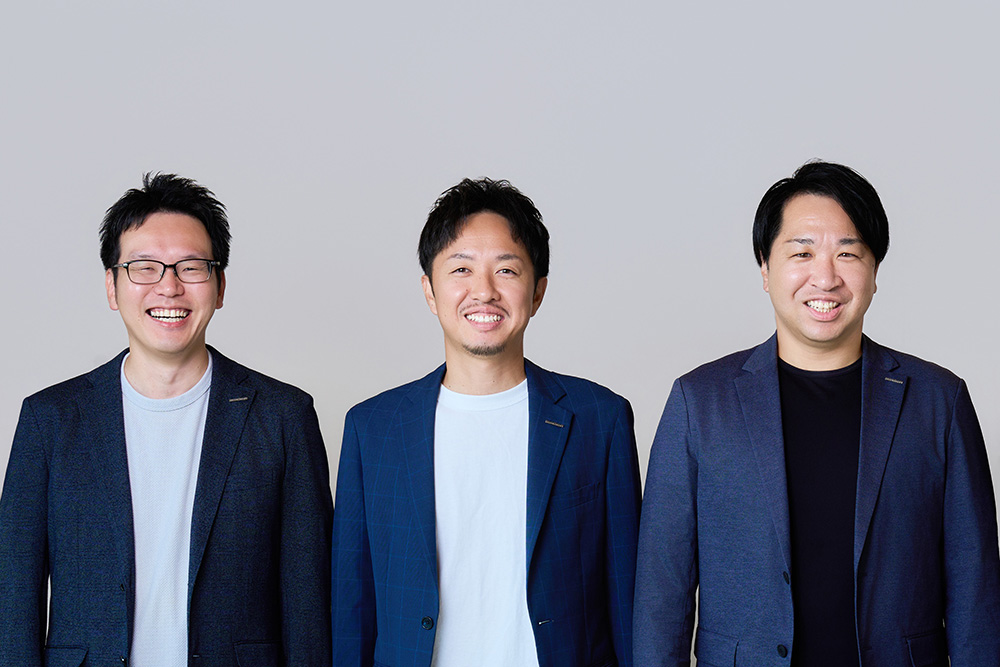

今回は東京プロマーケットへのIPO(上場)に至るまでの道のりについて、代表取締役社長の鶴(つる)厚志さん、専務取締役の鶴結介さん、経営管理部の眞國(まくに)慶多さんに話を伺いました。
お三方ともに大学時代にアルバイトとしてハンワホームズに関わり始め、当時は社員数4〜5名のいわゆる零細企業。そこからIPOに至るまでの約12年間の歩みや思いを語っていただきました。
彼らがいかにして“商店”から“企業”へと歩みを進めてきたのか、その軌跡をご覧ください。
目次

(社長)
まず、私と専務は兄弟で、父親がハンワホームズの創業者であり、私は大学時代に父親から声をかけてもらう形でアルバイトとして関わり始めました。
眞國さんは大学と学部が同じ友人であり、私が声をかけてアルバイトとして手伝ってもらうことになりました。
今ほどの事業規模もなかった為、当時は新しい事業の模索もしており、インターネットが流行し始めた時代でもあったことから「インターネットで何かできたら面白いのでは」という発想で色々なことにチャレンジし、最終的に立ち上がった事業が今のDEPOS事業(家具・雑貨のEC販売)です。
(専務)
2人が実家で仕事をしていたこともあり、少しずつ興味を持つようになり、EC事業が立ち上がった半年後くらいに私も関わり始めるようになりました。
就職活動もしてみたものの、自分たちで立ち上げたEC事業の運営がとにかく楽しく、就職活動にもあまり本腰を入れて取り組んでいませんでした。
結局、自分たちでやっている事業以上に面白いと思う仕事に出会うことはなく、2009年に大学を卒業してそのままハンワホームズに就職しました。
(社長)
私は、父が心筋梗塞で倒れたこともあり、大学を卒業した2008年にハンワホームズに就職しています。眞國さんは大学卒業後に東証一部上場企業に就職したのですが、私が声をかけて戻ってきてもらいました。
(眞國)
社長から声をかけてもらったタイミングは就職して1ヶ月半後くらいのタイミングでしたが、一般的なサラリーマンとして働いていくよりも、自分たちの事業を伸ばしていく方が面白いと感じ、ハンワホームズに戻ることにしました。

(社長)
私が就職したタイミングで社員が4〜5名ほど、役員も含めて10名程度の組織で、売上で言うと、年間約1.4億円でした。
その後、4年単位で大きく3つのフェーズに分けられます。
まずは父親と二人でとにかく創業事業である外構事業の成長にコミットするフェーズ。
その次は、外構事業だけでなく我々3人で立ち上げたEC事業をさらに加速させるフェーズです。このフェーズで貿易事業にも挑戦し始めました。
その後の4年間は、私自身も経営について考え積極的に関わり始めるようになった時期であり、この時期があったからこそ、事業継承後も比較的スムーズに経営ができたのではないかと感じています。
(専務)
最初の8年間で5〜6億円くらいまで成長し、その後の4年間で10億円くらいまで成長していたと思います。
(専務)
人材に投資したことが一番大きかったと思います。
私が入社した当時はまだ資金的に余裕もありませんでしたが、少しずつ売上が上がっていく中で人材に投資するだけの余力が出てきたため、人の採用に力を入れて、営業力を高めていきました。

(社長)
事業継承した家業を「企業」に変革していくためです。
建設業から始まったビジネスということもあり、社会に対する責任をもとに事業を運営していくべきだと考えていますので、そういった意味でも、IPOは自然な流れであると思いました。
眞國さんと専務にも相談しながら準備を進めることにしました。
(専務)
実は1年目はIPOを実現することができず、2年目にIPOしているのですが、1年目に関しては正直あまり当事者意識を持てていたわけではなかったです。
1年目でIPOを果たすことができなかったものの、それでも諦めずに「来年IPOを目指す」という社長の熱意に後押しされて、2年目は自分ごととして捉えてIPO準備にコミットしていました。
(眞國)
私は上場を目指すことには肯定的でしたが、自分自身の経理業務に関する知識・経験という点では不安も感じていました。
当時は経理業務を担当し始めてまだ半年も経っておらず、決算作業も怪しい状態でした。実際、監査法人とのやり取りでは専門用語が理解できず、何を答えればいいのか分からない状況でした。
ただ、上場準備を進めていく中で、知識も経験も少しずつ積み上がり、上場を達成することができました。

(社長)
この道しか、会社が成長し生き残っていく方法はないと思っていました。
確かに、IPO準備にはものすごくお金がかかりますし、社員にも負担がかかります。実際、社内ルールの整備などに抵抗を感じた社員が離れ、業績不振にも陥りました。離れたのは古株メンバーや、実力をつけて独立していった人たちでもあったので、競合にもなり得ますし、残ったメンバーへの心理的な影響も大きかった。二重三重の意味で大変で、心が折れそうになる瞬間もありました。
それでも、「ここを乗り越えられないなら、本当にやりたい事業や描きたい世界なんて実現できない」と思い、挑戦を続けました。「やり切ることが次のステップにつながる」と強く信じていたので、「やるしかない」という気持ちでした。
(社長)
私のように「家業に生まれた長男だから継ぐ」というケースは世の中にたくさんあります。
ある意味それは運命で、そのまま流れに乗って終わる、というのも一つの生き方ですが、私は「経営者になるために生まれた」という自分の使命を最大限全うしたいと思っており、そのために挑戦を続けようと思っています。
具体的には、企業価値や産業価値を高め、社員の幸福度を上げていくことが私の役割だと考えています。
だからこそ会社を売却するのではなく、オーナー家のコントロールを残したまま資金調達を行い、挑戦を続けて企業価値を高めていく。その手段としてIPOが最も適していたので、そこに向けて頑張れたのだと思います。

(社長)
信用力が格段に上がり、次のステップ、さらにその次のステップへと進める基盤ができたと感じています。
また、社会に対して責任を果たさなければならない。その意識も強まっています。
我々の事業は建設業をベースにしたものですが、公園を作るPFI事業など、社会と直結した分野を担っており、自分たちのことだけではなく、社会全体のことを考える視座を持つべきだと昔から考えていました。
そういう意味では、IPOは非常に自然な流れの中にあり、私にとっても会社にとっても必然だったと考えています。
(専務)
私は大きく2つあると思います。
一つ目は、採用の観点です。
採用難と言われているこのご時世ですが、大阪の片田舎の企業であるにも関わらず非常に優秀な方がエントリーしてくださっています。
以前と比べると、かなりエントリー数が増えていますし、非常に優秀な方からもエントリーいただいています。
二つ目は、自分自身の意識です。
もともとは家族企業という形でしたが、今では非常に多くのステークホルダーの方々に関わっていただいており、自分や会社の意思決定と行動に伴う社会的な責任を日々強く感じています。

(眞國)
私も専務と同じようなことを感じています。
IPO前は”商店”のようなイメージで、社長の意思決定で全てが決まるといった側面もありましたが、意思決定のフローや就業規則といった、基本的な部分も含めきちんと整備するプロセスを経て、「企業」としての役割や責任を理解していきました。
また、IPO前は決算など数字的な部分はあまり意識できていなかったのですが、管理部長として数字と向き合う中で、責任感や意識は大きく変わったと思います。
(社長)
会社の内部を整備していく必要があったり、多くのステークホルダーの意見を聞く必要があったり、様々な変化がありましたが、私は天才肌な経営者ではないので、たくさんの方から意見をいただきながら経営をしていくスタイルは自分に合っていると感じています。
上場企業の社長になって良かったと思っています。
(専務)
高い成長性を追求しつつも、安定性という点も押さえながら、両者のバランスを高いレベルで保っているという点が経営者としてとても稀有なのではないかと思います。
いわゆるIT系のスタートアップの起業家のように成長性を追求し事業をどんどん展開していくタイプの経営者は多くいらっしゃると思いますが、我々は社会のインフラに関わる事業を行っているので、安定性といった点も非常に重要になります。
レガシーな産業を変えようとしつつも、社会インフラに関わっている企業としての自覚、それこそ社会的責任を負う覚悟がある経営者だと感じています。

(眞國)
良い意味で「創業家っぽくない」と感じます。
例えば、色々な監査法人さんとやり取りをさせていただきますが、その際に「不要と思えるような支出が本当に少ない」と言われることが多いです。それは「企業価値を高めていく」ということにフォーカスし、その目的を果たすために資金を使っているということが客観的にもわかる、ということです。
こうした姿勢は上場企業の社長に求められることなので、確かに上場企業の社長として適していると感じます。
(社長)
日本は人口減少が進んでいることもあり、建設業のようなレガシー産業は厳しいと言われています。働き手も減りますし、サービスを求める人も減っていくと予測されます。ただ、この国は災害が多いことから建設業は必要不可欠で、必ず維持しなければならない産業です。
大きな課題は「資本主義の中で経済価値にどう置き換えていくか」ということであり、これは私自身が人生を賭けて取り組む大きなチャレンジだと思っています。
この課題を解決するために、資本市場の活用方法や、M&Aや新規事業などを含めた多角的な経営戦略について、経営陣とは日々議論を進めています。
ただ、人口減少が進む日本で新しいビジネスモデルを築くことができれば、それは必ずグローバルでも通用するとも考えており、非常に前向きに捉えています。難しいフェーズにある国だからこそ、挑戦する意義があり、やりがいもあると感じています。

(社長)
お客様に対しては、もっとライフスタイルに合った空間や過ごし方を提供していきたいと思っています。
これまで日本は「安定した工業製品を生産する」という点で世界的にも評価されてきましたが、今は多様な価値観が広がったことで、ライフスタイルに合った空間や過ごし方が求められるようになっていると感じます。
私たちが提供しているサービスはそうした新しい選択肢になれると信じているので、この市場でマーケットリーダーになり、産業全体の価値を高めていきます。
従業員に対しては、レガシーな産業だからこそできる多様な挑戦の機会を提供していきたいと思っています。
我々は「空間」というソリューションを提供していますが、その手段は無数にあります。
たとえば、屋外空間創造事業の一環で、ECや貿易事業に取り組んでいるので貿易にも挑戦できます。その他にも「海外の文化を日本に輸入したい」であったり「海外で流行っている食事を日本でも提供したい」というのも「空間」につながります。
ブリッジパークプロジェクト(りんくう公園の開発)や、ビーチサッカーワールドカップの誘致に挑戦しているのもその一例です。
レガシー産業だからこそできないのではなく、逆にできることがたくさんある。そういう可能性を社員にも感じてもらいたいし、社会にも伝えていきたいと思っています。こういった構想を着実に形にしていき企業価値を高め、更には産業全体の価値を高めながら、世の中に貢献していきます。